半年後にあなたは100%確実に死を迎える。そればかりか貴方の家族・友人なども全員同じ運命を共にすることになる。……そういう状況におかれたとしたら、貴方は最後の日まで日常生活を普通に送れるだろうか、それとも……。
渚にて―人類最後の日 を読了した。
1950年代SFの名作の一つに数えられる作品だが、この小説をSFとして読む必要はない。この小説には超能力を持つスーパーヒーローも超科学的な装置も出てこない。登場人物の誰もが至って普通の市民であり、時は静かに流れていく。話の発端こそ未来SFらしく第3次世界大戦という全面核戦争ではある。しかし、話の主題は「核兵器の非道さを訴える」なんてものではない。そんなものとは全然関係ないところにあるのだ。
コバルト爆弾の雨を降らせあった結果、北半球諸国は放射能を帯びた大気に覆われて全滅。オーストラリアは戦争に直接荷担しなかったため即時全滅は免れたが、大気の対流により、北から順に放射性元素を濃厚に含む空気に覆われ、生物が生育できない状態に陥ると予測された。おそかれ早かれ地球全土は汚染した大気に覆われて全ての人間は死ぬ。逃げ場はないのだ。
アメリカ合衆国の潜水艦スコーピオンは、たまたま南方で活動していたために生き残りオーストラリア海軍の指揮下に入ることになる。その艦長ドワイトと、彼に恋するオーストラリアの娘モイラ、この二人を取り巻く幾人かの人物たちの半年が淡々と描かれる。
艦長は事態を理解していながらも、とうに死んだはずの妻と娘と息子のことを現在形で語り、息子への土産として上等な釣りざおを買い、釣りのコツを教えてやることを夢想したりしている。彼の部下ピーターと妻は、それが完成したときには既に誰も見る者は居ないことを知っていながら、庭の模様替えと植物の植え替えに余念がない。一方、潜水艦で彼らと一緒に仕事をした科学者オズボーンは本来なら購入などありえなかったであろう高価なスポーツカーを手に入れ、死者続出の命がけのカーレースに出場して爆走する。若い娘であるモイラは、自分に将来というものがないという事実に押しつぶされ酒におぼれているが、どんなときにも規律とけじめを重んじる艦長に感化され、タイピストの訓練を始める。おそらくそのスキルを役立たせる機会は永遠にやってこないのだが。
そんな中、予測どおりに北から順に都市が放射性の空気に飲み込まれて沈黙していく。苦しまずにすぐ死ねる毒薬のパッケージが無料で配布され始める……。
そして、ついに彼らの住む町にも「そのとき」がやってくる。
死はいつか誰にもやってくる。しかし、その死が極めて近いうちにやってくると告げられたら? その上、何かを遺したとしてもそれを見る者が誰一人居ず、自分の子供たちも自分と同時に死んでしまうとしたら?
そんな中でも、人はこの小説の登場人物たちのように「日常生活」を続けられるものなのだろうか? また、本当に幸せで充実していたといえる人生とはいったいどのようなものなのだろうか?
本エントリーの初出:チャンネル北国TV (2005-03-07)
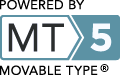










コメントする